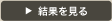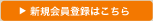500回聴いた曲に、今またドキドキする
リー・リトナー『ジェントル・ソウツ』
ファイル形式:WAV 96kHz/24bit

いきなり頂上決戦
では、今回からは実際にハイレゾ音源を聴いていきます。まず問題は、最初に何を聴くかということ。初めてのハイレゾで初めての曲を聴き、「ああ、いい音」というのもいいんだけれど、やっぱりまず「CDとどう違うのか」を確認、認識しておかないといけませんね。「優秀録音CD」と違いがなくなってしまいますから。
そして選んだのは、リー・リトナーの『ジェントル・ソウツ』(JVC)。スペックはWAV 96kHz/24bit。この『ジェントル・ソウツ』は1976年にダイレクト・カッティングという方式で録音、LP制作された音源がオリジナル。ダイレクト・カッティングは、スタジオで演奏された音をディスクに直接(ダイレクト)溝を刻む(カッティング)方式。通常はマスターテープを作り、そこからカッティングするわけだけど、テープに録音するというプロセスを経ないので音がいいという究極のLP録音手法でした。しかし、この方法はバンド全員同時録音、かつLP片面20分ほどをひと続きに演奏しなければならず、途中で失敗すると片面の録音が全部やり直しという、演奏者に非常に負担のかかる方式でした。でも、それが緊張感のある演奏を生むというメリットにもなり、結果として、音よし、演奏よしのアルバムとなって、フュージョンの名盤として聴き継がれています。
そしてCD化の際には、ダイレクト・カッティングと同時にテープ(オープン・リールのアナログ)でも収録されていたものがマスターになっています。CDの解説によれば、そのテープ・スピードは秒速76センチ。この速度は当時の通常マスターテープの2倍です。これは当時の最高録音スペックですから、CDでも音質は非常によいのです。実は私マスターは発売時リアルタイムでダイレクト・カッティングのLPを聴き、CDでもXRCDでも聴き続けてきました。このアルバムが好きなんです。まあ少なく見積もっても500回は聴いていますね。
前置きが長くなりました。この「優秀録音LP~CD」とハイレゾはどう違うのか。このような高音質かつ愛聴盤を、今501回目(?)をハイレゾで聴いて、はたして新たな発見があるのか。予選第1戦がいきなり事実上の決勝戦みたいな展開ですが(笑)、好きなB面3曲のメドレーを聴いてみた。
続きはこちら>>
音が伝える音以外のこと
結論から言うと、最初から最後まで驚いた。この演奏はエレクトリックのフュージョンだから、アコースティックのジャズとは違って、空間の響きとか「生」の音を狙ったものではなく、「音」を作り、がっちりとバランスを整えて、レコードという「録音作品」を作り上げたもの。だからさすがに聴こえなかった音が聴こえたなんてことはないし、これまでのCDが「よくない音」になってしまったという感じはない。でも違う。「印象」が大きく違う。まず「ドキドキした」。30年以上も前、初めてこの演奏を聴いたときの感動がよみがえったというと大げさ過ぎるかな。
1曲目「キャプテン・フィンガーズ」は、ギターとサックスの一糸乱れぬ長い長いユニゾン・プレイが聴きどころ。実にスリリングな演奏なんだけど、印象が変わりましたね。けっこう荒々しい。こんなにシャカリキな感じだったっけ? 今までよりも緊張感がぐっと増している。思わずスピーカーに向かって乗り出してました。それと、キーボードの存在感が違う。キーボードもギターとサックスのアンサンブルにしっかりとからんでいてバンドの一体感が強まったよう。もちろんCDと音のバランスは同じなのに、不思議だな~。ただドラムスとパーカッションは音が違う。いや、楽器の音自体は変わっていないんだけど、そこに空気があるというか、ハイハットが踏まれるたびにそこから空気が出ている感じがする。パーカッションも同様。楽器のまわりに空間があるのね。厳密には音の違いなんだろうけど、ことさら「ほら、違うだろ」と耳に訴える感じはない。空気「感」というものだな。
驚きながら聴き進めて、3曲目「ジェントル・ソウツ」。3曲目といっても20分におよぶ3曲メドレーなんだけど、後半はなにかホッとした空気が漂っているのが感じられる。最初に書いたように、このアルバムはダイレクト・カッティングだから、20分最後の1音に失敗しても全部がパー。最後まで演奏者の緊張は続いているだろうけど、最初とはちょっと表情が違う。ここまでくればあとは安心というところなのかな。ガチガチの緊張で始まり、最後でホッとしているという流れを感じましたね。CDでこんな印象を持ったことはなかった。なにか、バンドの演奏を目の前で見ているような気分。これがミュージシャンの息づかいというものか。
ああ、そうか。これは録音現場のプロデューサーの気分なのだな、きっと。音楽を聴くと同時にミュージシャンの気持ちも感じているんだ。ハイレゾは、スペック的にはマスターテープそのものだから、再生装置は違うけれども、これは現場に最も近い音といえる。マスターテープには耳に聴こえる音のほかにも、何か入っていたということなんだな。
これまで好きで500回も聴いていながら、501回目でまた新たな感動ができるなんて、なんてすばらしいことだろう。ハイレゾで音そのものが変わるという音源もあるだろうけど、それを超えたところにこそハイレゾのほんとうの魅力があるとみた。いきなり頂上決戦は失敗だったな。もうCDには戻れないものね。
●ハイレゾ音源配信サイト

●ハイレゾ対応機器のご紹介