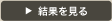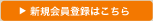ジャズの進歩というのは、連続性の中にある。約100年のジャズの歴史にあって、とりわけ革命的な進歩といわれるチャーリー・パーカーらが作り出した新しいアドリブ手法「ビ・バップ」にしても、その前のスイング・ジャズの手法、つまりジャズの歴史をしっかりと踏まえたものだった。まず新しい考え方を加え、奏法を変え、リズムを変え、フレイズを変えて新しい「スタイル」を作り出したわけだが、それがまったく違うものだとそれは別の音楽になってしまうから、要するにその以前のスタイルからの連続性があるから「ジャズ」としての歴史となる。 さて、ジャズ・ヴォーカル。これは「新しいもの」というふうに変わっていくことが難しい。100年前の、まだジャズ・ヴォーカルという呼び名はなく、のちにジャズ・ヴォーカルの元祖みたいに振り返られる歌と今のジャズ・ヴォーカルが大きく違うところはあるだろうか。「歌」というのは非常に根源的な表現であり、「ジャズ」とは呼ばれるが、器楽演奏のジャズと異なったものだ。もちろんスキャットで楽器のようにアドリブ・ソロをする人もいるが、それはむしろ器楽演奏の歴史の流れの中に位置するものだと思う。最初のスキャット・ソロといわれるのはトランペットの名手、ルイ・アームストロングの演奏だが、これはトランペットの代わりというふうに聴いたほうが歴史の流れとしては自然だろう。 と、めんどうくさいことをヴォーカリスト、セシル・マクロリン・サルヴァントの新譜『フォー・ワン・トゥ・ラヴ』を聴いて考えた。セシルは2013年に『ウーマンチャイルド』(彼女の2作目)を発表し、まだ新人にもかかわらずグラミー賞の最優秀ジャズ・ヴォーカル・アルバム部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた。驚くのはそれだけでなく、アメリカのジャズ専門誌『ダウンビート』の国際ジャズ批評家投票で「年間ベスト・ジャズ・アルバム」に選ばれたのだ。これは世界中のジャズ評論家154名の投票によるもので、60年ほど前に始まった同投票で、ヴォーカルのアルバムが「ジャズのベスト」に選ばれたのは初めてのことという。 『フォー・ワン・トゥ・ラヴ』はその『ウーマンチャイルド』に続くアルバム。音楽的には前作と大きく変わるところはない。アルバムにはオリジナル曲や、アメリカのスタンダード・ナンバーやフランス語によるフランスのポップスのカヴァーが収録されている。バックはピアノ・トリオ。アレンジもじつにオーソドックスな、形としては数多いジャズ・ヴォーカル・アルバムとなんら変わらない。セシルは1986年生まれ。マイアミ出身、ハイチ人の父とフランス人の母をもち、2010年にセロニアス・モンク・ジャズ・ヴォーカリスト・コンペティションで優勝という経歴をもつが、このバックグラウンドとて、現在ではめずらしいというものではないだろう。 そこで、話は最初に戻る。変わっていくこと、新しいことに価値を見出しがちな「ジャズ」にあって、ことさらそれにこだわっていない(ように聴こえる)彼女の音楽がどうして世界中のジャズ評論家をうならせたのか。それもなぜ圧倒的に多い器楽演奏の「ジャズ」を抑えてベストと評価されたのか。つまり、すぐれたジャズ・ヴォーカルってなんだろうと考えさせられたわけ。「ジャズ」には新しいことなんか必要ないのかな。それはジャズ・ヴォーカルだけのこと? じゃあジャズの進歩ってなんなんだろう? そもそもジャズの面白さって? でもうまく説明できないけれど、たしかにすばらしい感動があります、これは。ぜひあなたの耳で聴いて、あなたも考えてみてください。