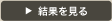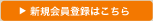ファースト・アルバムが2009年度「デンマーク音楽賞・最優秀国内ジャズ・ヴォーカル作品」を獲得という輝かしいデビューを果たしたシゼル・ストーム。以降コンスタントに活動を続け、今回の『クローサー』は4枚目のアルバムとなる。
内容はオリジナル全10曲のうちスタンダードと自作が半分ずつ、これに日本盤ボーナス・トラックでスタンダード2曲が加わる。名曲に挟まれるように並ぶ自作曲(すべてシゼルとプロデューサー、ペーター・オットの共作)もいい流れを作っている。最初から12曲目の最後まで一気に聴いてしまうこと間違いなしの、充実した内容。シゼルには「北欧の美人ヴォーカリスト」という紹介文がついてまわるが、それはなくとも耳のいい人はもうすっかりファンになっていることだろう。
このアルバムには、シゼルのこれまでのアルバムにはなかった大きな魅力がある。1曲目「ウォーキング・ブラインドリー」のイントロの、深く柔らかいピアノの響きからそれは感じられる。まず、音が素晴らしいのだ。そしてふわっと浮き上がってくるシゼルの声の響きにハッとする。次いでベースが最初にソロをとるのだけれど、ここで音色だけでなく、全体の音の感じが一般的なヴォーカル+ピアノ・トリオとはちょっと違うのではないかと気づき、続いてソロをとるピアノの音でその印象は決定的になる。なんというか、どの楽器にも「存在感」があるんだな。ナチュラルなサウンドというのではなく、音色と響きが独特だ。この特徴は、パソコンのスピーカーで聴いてもはっきりとわかると思う。
一般的には、当然主役のヴォーカルに大きなスポットを当てるようなバランスでミックスするわけだが、ここではヴォーカルも含めてメンバー全員がまるでカルテットのように対等な位置にあるように感じられる。1曲目に入るストリングスはぐっと引っ込めてほんの味付け程度にしているのもヴォーカル・アルバムらしくない。2曲目の「四月のパリ」ではトランペットが入るが、後半のヴォーカルとのからみでも、ヴォーカルに寄り添うというよりは、デカい音での競演だ。3曲目のヴォーカルとトランペットによるメロディのユニゾンも同様。今作の基本メンバーは2013年の前作『ナッシング・イン・ビトゥイーン』と同じであり、各曲ともにバックのソロがふんだんにフィーチャーされていることからしても、これは「バンド」という考えで録音されているのだなと想像する。もちろんそれはシゼルの意向を汲んでのことだろうが、それを見事にまとめ上げたエンジニアの実力も注目すべきこと。と思ってクレジットを見ると、なんとエンジニアはヤン・エリック・コングスハウクだった。知っている人は知っている、あのドイツのECMレーベルの「ECMサウンド」を作り上げたエンジニアである。ミックス、マスタリングされたのはその本拠地であるノルウェイ、オスロのレインボー・スタジオ。ああ、この音の独特な感じというのは、ECMに近いものだったんだな(ECMにはこんなにスウィンギーなジャズ・アルバムはないので、比べようがないけれど)。改めて録音された「音」の重要性に気づかされる。
このように『クローサー』は、歌はもちろん、選曲にも音にも隅々にまで気が配られており、それはちゃんとリスナーに伝わってくる。長く聴き続けられるであろう充実した作品だ。